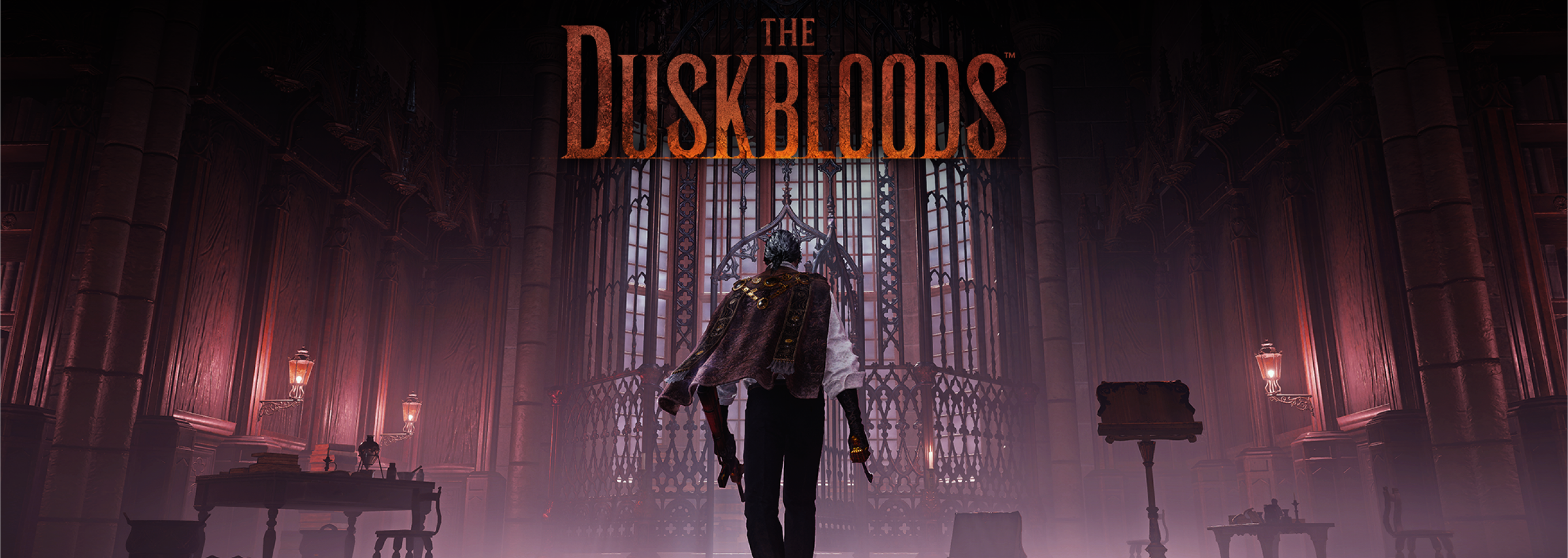簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
フロム・ソフトウェア※1の宮崎です。本作のディレクターです。
※1株式会社フロム・ソフトウェア。ゲームソフト開発・販売会社。『ELDEN RING』などのタイトルを開発しており、Nintendo Switchでは『DARK SOULS REMASTERED』を発売。

まずは、本作がNintendo Switch 2 で発売されることになった経緯をお聞かせください。
これはかなり前の話になりますが、たまたま任天堂さんとお話しする機会がありまして、
その時、本作の原型となるようなアイデアをお話しさせていただいたんです。
具体的な企画案というよりは、とりとめもない私の妄想のような話でしたし、
我々が手掛けてきたタイトルとはまた違った形式のアイデアだったのですが、
任天堂さんはとても積極的に話を聞いてくださり、興味を持っていただけました。
それが、このプロジェクトの契機です。
最初はNintendo Switch向けのタイトルとして小規模に開発を始めたのですが、
ゲームの骨格が見えてきて、開発の規模も大きくしていこうかというタイミングで
Switch 2の話をいただきまして、改めてそちら向けに開発を仕切り直したのです。
本作のアイデアをしっかりと実現するために、
オンライン要素も重視した新ハードは、とても魅力的でしたので。
これまで手掛けられてきたタイトルとまた異なる形のものなんですね。本作はどのような内容のゲームになるのでしょうか。
形式としては「PvPvE」※2になるかと思います。
オンラインマルチプレイをベースとし、プレイヤー同士の戦い、プレイヤーと敵との戦い、どちらもあるタイプのゲームです。
※2プレイヤー同士が戦う「PvP」と、プレイヤーと敵(CPU)が戦う「PvE」の要素が合わさった、複数のプレイヤーとゲーム内に登場する敵(CPU)が入り混じって争う形式の総称。

宮崎さんの中で、元々PvPvEのゲームを作ってみたいという気持ちは、漠然とでもあったのでしょうか?
そうですね。以前から、PvPvEという形式は、とても面白く、ゲームデザインの幅もありそうだと思っていました。
また、我々フロム・ソフトウェアが今まで培ってきたノウハウ、手応えのある敵を作る経験などが、しっかりと活かせそうな形式であることも魅力的でした。
あと、本筋とは外れてしまって申し訳ないのですが、一点触れさせてください。
お話ししたように、本作はオンラインマルチプレイをベースとしたタイトルですが、
これは、我々が今後、そうした方向性に大きく舵を切っていく、ということではありません。
Switch 2 版の『ELDEN RING※3』も発表されましたが、ああいった、我々の従来の方向性、
シングルプレイメインのゲームも、引き続き積極的に作っていくつもりです。
その点は、ここで明確にさせてください。
※32025年発売予定のNintendo Switch 2 ソフト『ELDEN RING Tarnished Edition』。広大なフィールドを舞台に、プレイスタイルに合わせてキャラクターを育成し、冒険するアクションRPG。
本作のキャラクターや舞台について教えてください。
本作の主人公というか、ユーザーさんに操作していただくキャラクターは、「血族」と呼ばれる存在です。
彼らは、特別な血の力によって人間を超える力を得た一族で、一般的な概念でいうと吸血鬼のようなものですが、いわゆるホラーの恐ろしい怪物のイメージではありません。
吸血鬼あるいは「血」というワードから、特にロマンの側面を我々が勝手に抽出して、
それを拡大解釈したような存在が、本作の「血族」となります。

血族たちは「始まりの血(ファーストブラッド)」と呼ばれる存在を巡って争っています。
そして「始まりの血」は、人類の時代が終わろうとする時、「人類の黄昏」に流れます。
血族たちは、さまざまな場所、そして時代の「人類の黄昏」に召喚され、
「始まりの血」を巡って争うことになる、という訳です。
なので、本作の舞台は特定の場所、そして時代ではありません。
ゴシックあるいはヴィクトリアンの雰囲気を持った王道のマップもあれば、動画トレーラーでもちらと映っていた、列車などが走る、近代末期といった雰囲気のマップもあります。

『The Duskbloods』というタイトル名に込められた意味を教えてください。
意味としては「黄昏の血族」ですね。
先ほどもお話しした、人類の黄昏に召喚され、始まりの血を巡って争う血族たち、
彼らを「黄昏の血族」と呼ぶイメージです。
言うなれば、ユーザーさんに操作していただくキャラクターたちの総称ですね。

本作では「血」がゲームにおけるカギになるのでしょうか。
はい。一言で「血」と言っても、ゲーム的なダメージ表現などを含む、物理的な意味での血よりは、より概念的な側面を重視しています。
そこに蓄積する歴史、継承される力、刻まれる運命といったもの、人を超える者たちの永遠の営みの象徴としての「血」が、本作のキーワードのひとつです。